一般社団法人 通信研究会
〒101-0052
東京都千代田区
神田小川町1丁目6番地3
B.D.A 神田小川町ビル5階
TEL: 03-5298-6110
FAX: 03-5298-6113
お問い合わせはこちら
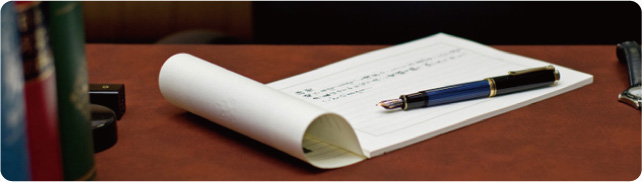
通信研究会のご案内
事業報告
令和5年度事業報告
第58期(自 令和5年4月1日~至 令和6年3月31日)の決算にあたり、当社団の事業概況についてご報告申し上げます。
5月8日新型コロナウイルス感染症の5類移行後、働き方改革と称してテレワークが推奨され、人々の行動変容を促す措置が取られ生活様式、働き方、社会構造の変革の契機になる側面が期待されましたが、首都圏に転入者が増え従来に戻りつつあります。
政府が推進している地方創生施策は、「デジタル田園都市国家構想」に変わり、デジタル技術を一層活用して、少子高齢化、人口減少問題について国民意識の共有化を図り、人口減少の歯止めと地域経済縮小の克服をめざし、東京一極集中の是正を行い、地方の復興を図り、若い世代の人達が安心して就労、結婚、子育てができる地域社会を実現することを引き続き目標としています。大都市圏から地方への人の流れ、関係人口、観光・交流人口の拡大、移住・定住人口の促進をめざし雇用の確保に向け取り組んでいるところです。
人口減少による過疎地域の拡大、自治体の支所機能の統廃合による公共サービスの低下が散見されるようになりました。今後、安全、安心、交流の拠点、生活インフラとして地域コミュニティの中で、ユニバーサルサービスが課されている郵便局の役割・位置づけはますます大きくなっています。
現在、郵便局ネットワークにより国民に提供されるユニバーサルサービスについては、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社の責務として法定され、郵便局窓口において金融ユニバーサルサービスを提供することになりました。ユニバーサルサービスは、国民生活に必要不可欠な基礎的サービスを過疎地も含めすべての地域で誰もが利用可能な価格で安定的に提供できることとされ、これらの特徴を併せ持つサービスがユニバーサルサービスであるとされています。しかし、ユニバーサルサービスを提供し続けるのにはコストがかかり、そのコストを誰がどのような形で負担をしていくのかという大きな問題が残っています。ユニバーサルサービスを維持するということは一定の範囲で赤字サービスを提供し続けるということになるのです。
平成31年4月1日から適用された独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律では、郵便局ネットワークの維持を支援するための交付金及び拠出金の制度を新たに創設しました。また機構の名称を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」と改め、令和6年度は、日本郵便に3,030億円交付する予定ですが、この制度のメリットは金融2社にあり消費税が減免された金額が郵便局ネットワーク維持の為にどのように活用されているのか明確になっていません。この交付金・拠出金制度の更なる算定の見直しが必要になってきます。
郵便事業全体の事業収益の長期低落傾向に対して、ユニバーサルサービスの提供に影響を及ぼさないようにするため郵便法の改正が令和2年11月に与野党一致で成立し、さらに令和5年12月郵便料金の一部値上げの省令案が諮問され、本年10月に郵便料金の一部値上げが行われる予定です。ユニバーサルサービスのコスト負担の問題は、将来的には国民全体として捉えていく必要があります。ユニバーサルサービスが課され、日本全国にきめ細かなネットワークを持って、公共サービスを行っているのは郵便局だけです。郵便局を通信、物流、金融の拠点、さらに社会資本として行政と生活の代行機能を併せ持つことができれば、日本郵政グループの企業価値も向上するものと思われます。
郵政民営化法は日本郵政グループ各社とのシナジー効果を最大限活かし、効率的なグループ運営を発揮することを目指したものと受け取られています。
今後、株主の増加により株主利益の最大化と効率化・合理化、改正法の趣旨である地域性及び公共性をどのように維持していくことができるのか、バランスのとれた経営が求められてきます。
会員のニーズに応えるべく、機関誌『逓信 耀』の誌面をより一層充実させるため、毎月企画編集会議を開催し、焦点を明確にして全国各地に取材を行いました。編集方針については、日本郵政グループ各社の経営戦略を分析し、郵政民営化法等改正法によって、収益性のみならず公益性及び地域性が求められる郵政事業について、さまざまな角度での検証を行い、その問題点と課題を浮き彫りにしました。また、シリーズ「地方創生のいま、地域を元気に!」では取材を通して地方創生の意義、地域における郵便局の役割等を紹介することが出来ました。さらに「地方創生における地方自治と郵政事業」では、市町村長から郵便局と地方自治体との連携施策、郵便局が地域社会で果たしてきた役割等について意見を伺うことが出来ました。全国の郵便局長にご協力いただき、インタビューや各種座談会等を通じて、地域社会に貢献する郵便局の実像や今後の展望等について掲載することが出来ました。
公益目的事業として行った「大学生の視点を生かした農山村集落活性化と郵便局との連携可能性について」(福島大学岩崎由美子教授他)、「競争時代を迎えた国内外における情報通信・金融・物流事業の現状と「地域再生」の視点から見た今後の郵政事業の在り方【地方自治体から郵便局への支所機能移転に関する調査研究】」(滋賀大学経済学部横山幸司教授)等の研究報告会を開催することができ、いずれも時宜を得た大変有意義な報告会で、資料を関係機関に配布致しました。また全国各地に講師派遣等を行い会員のニーズに応えることができました。
《理事会開催》
○ 第1回
令和5年 4月25日(火)アルカディア市ヶ谷7階「雲取の間」
・令和4度事業報告(案)及び収支決算(案)について
・公益目的支出計画報告について
・令和6年度総会日程について
・その他
○ 第2回
令和5年 5月22日(月)アルカディア市ヶ谷7階「妙高の間」
・当面の諸課題について
・その他
○ 第3回
令和5年 8月28日(月)アルカディア市ヶ谷7階「雲取の間」
・第1四半期事業報告及び収支決算報告について
・その他
○ 第4回
令和5年11月28日(火)アルカディア市ヶ谷3階「天城の間」
・第2四半期事業報告及び収支決算報告について
・令和6年度公益目的事業計画変更について
・その他
○ 第5回
令和6年 3月21日(木)アルカディア市ヶ谷7階「妙高の間」
・第3四半期事業報告及び収支決算報告について
・令和6年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
・その他
《総会開催》
○令和5年 5月22日(月)アルカディア市ヶ谷7階「妙高の間」
・令和4年度事業報告(案)及び収支決算(案)、会計監査報告
・令和4年度公益目的支出計画報告等について
・その他
○令和6年 3月21日(木)アルカディア市ヶ谷7階「雲取の間」
・令和6年度事業計画(案)及び収支予算(案)について
・令和6年度公益目的事業計画について
・その他
《調査・研究》
・郵便プラットフォーム上のビジネス展開案
大学生の視点を生かした農山村集落活性化と郵便局との連携可能性について
岩崎由美子福島大学行政政策学類教授他 ゼミ生等
・競争時代を迎えた国内外における情報通信・金融・物流事業の現状と
「地域再生」の視点から見た今後の郵政事業の在り方
【公民連携による様々な施策拠点としての郵便局に関する実証的研究】
横山幸司 滋賀大学経済学部・社会連携センター長 教授
《報告会開催》
○ 令和6年 3月11日(月)アルカディア市ヶ谷4階「鳳凰の間」
福島大学行政政策学類 岩崎由美子教授 他ゼミ生等15名
参加者30名
○ 令和6年 3月21日(木)アルカディア市ヶ谷7階「妙高の間」
滋賀大学経済学部・社会連携センター長 横山幸司教授
参加者30名
《資料集作成》
・「大学生の視点を生かした農山村集落活性化と郵便局との連携可能性について」報告書
・「公民連携による様々な施策拠点としての郵便局に関する実証的研究」報告書
《令和5年度新郵政事業ビジネスモデル調査研究委員会開催》
○第1回 令和5年9月27日(水)アルカディア市ヶ谷7階「白根の間」
○第2回 令和5年10月12日(木)アルカディア市ヶ谷7階「白根の間」
○第3回 令和5年11月28日(火)アルカディア市ヶ谷5階「赤城の間」
主な内容
*「デジタル時代における郵便局の新たな価値創造と持続可能な郵便局経営について」
・東京成徳大学経営学部 武井孝介教授
*「日本郵便による新たなビジネスモデルに関する研究」
・東京成徳大学経営学部 樋口 徹教授
*「日本郵政グループ決算概況について」
・明星大学経営学部 中島洋行教授
*「郵政民営化法の検証~作成過程の問題点とその弊害~」
・産経新聞本社 福島 徳企画委員
*「郵政民営化法等改正法の検証と日本郵政グループの資本政策の在り方、
今後の政治的課題等について」
・一般社団法人通信研究会 島﨑忠宏事務局長
≪寄付・寄贈≫ 公益財団法人 通信文化協会
令和5度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しないので、これを作成しない。
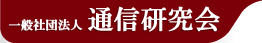
 ホーム
ホーム お問い合わせ
お問い合わせ リンク
リンク サイトマップ
サイトマップ
